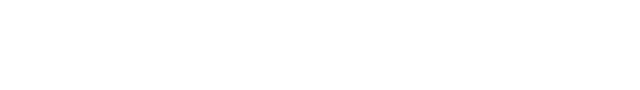「10分や15分話しただけで何がわかるのか、診断できるのか」(怒)について
診断に際し、「10分や15分話しただけで分かるのか」「発達障害の本を何冊も読んでいるが違うと思う」などと言われることがある。
診断を受け入れることが難しいことは十分に理解している。
すぐに受け入れてもらえるとも思ってはいない。
自分の説明に説得力がなく、力不足であることも自覚している。
診断までの時間が短い場合は、迷う余地のない典型的な症状(特性)があるということだ。
うちでは、事前に、生後から現在に至るまでの様子を6枚の問診票に記載していただいている。
それらを踏まえて、質問する内容などを決めている。
ある偉い先生と話した際、「子どもを5分見れば診断できる」とおっしゃっていた。
同じレベルの診断力を有する訳ではないが同感する。
小学校高学年くらいになると、診断を決めるまでの時間が長くなることがある。
他の子どもと同じように振る舞う(「カモフラージュ」)を身につけてため、判断が慎重になる。
ある場面だけを見て判断する(「スナップショット診断」)と診断を間違える。
判断が難しい場合には時間が長くなる。
例えば、落ち着きのなさについても、原因は一つではない。
注意欠如多動症の症状、慣れない状況での不安の強さの現れ、アタッチメント形成不全(いわゆる「愛着障害」)によるもの、授業中の落ち着きのなさであれば勉強の難しさなどが考えられる。
それぞれの可能性を考えながら、絡まった紐をほどくように、様子を観察しながら質問をしている。
診断を伝える際には、診断基準に照らしながら、その根拠を説明している。
また、診断をお伝えする理由もお話ししている。
診断をお伝えすることは、困りごとの解決に向けたプロセスのひとつであり、背景や理由を知ってもらうためである。
簡単に見えるが、やってみると難しいことはたくさんある。
毎日いろいろな車の整備をしているひとは、エンジン音を少し聞いただけで、車種や故障箇所が分かったりする。
料理人は出汁を口にしただけで、何から取ったものかが判断できたりする。
プロ野球選手は難なく打球を打ったり捕ったりする。
整備士、料理人、プロ野球選手といっても、持っているスキルなどは様々である。
自称を含め発達障害の専門家はたくさんいる。
発達障害の専門家として、今後とも、日々研鑽に励んでいきます。