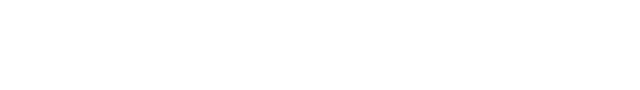(よくある誤解)「検査しないのですか」
自閉スペクトラム症や注意欠如多動症(ADHD)の診断をお伝えする際に、
「検査はしないのですか」と聞かれることがあります。
よくある誤解です。
「この検査をすれば、自閉スペクトラム症やADHDであるかがわかる」という検査は、存在しません。
診断は、これまでの生育歴とともに、おうちや学校などでの様子を聞き取り、質問に対する受け答えや行動など、子どもを観察して行うものです。
検査とは、発達検査(新版K式や田中ビネー)や知能検査(WISC)を指していることが多いです。
学校の先生やスクールカウセラーから、「(自閉スペクトラム症やADHDの可能性があるので)WISCをやってもらうように」と指示されて、クリニックに来られるひとが多くいます。
ネットニュースや新聞などで、発達障害の診断のためには、検査が必要と書かれていることが多いです。
発達検査は、姿勢・運動の領域を含め、発達状態を知るためのものです。
就学前までの子どもに実施されることが多いです。
知能検査は、全般的な知的水準とともに、特定の認知領域の知的機能を示す指標(WISC-Ⅴの場合、言語理解、流動性推理、視覚空間能力、ワーキングメモリーと処理速度)から、包括的に知能を測定するものです。
就学後の子どもに実施されることが多いです。
いずれも、診断のために行うものではありません。
そもそも、自閉スペクトラム症やADHDの診断基準には、発達や知的な遅れは含まれていません。
発達や知的に遅れがある場合には、「知的発達症」という診断がつきます。
また、標準化された評価尺度(ADI-R、ADOS-2、CARS2、ADHD-RSなど)がありますが、これらも診断のための参考資料にすぎません。
これらの結果で診断が決まるわけではありません。
脳波に関しても、発達障害が診断できる検査としての科学的根拠はありません。
同じ発達障害でもあっても脳波パターンには個人差が大きく、一貫性に欠けます。
定型発達のひとでも様々な脳波パターンが見られます。
そうしたこともあり、診断基準(DMS-TRやICD-11)においても脳波が必要とはされていません。
米国小児科学会などにおいても発達障害の診断目的での脳波検査は推奨していません。
ちなみに、知能検査にはメリットがありますが、事実上のデメリットもあります。
メリットは下記の通りです。
・ 全体的な知的水準がわかります。
・ 認知機能の特徴から、大雑把ながら、得意な部分と苦手な部分が分かります。
・ 検査中の様子から、課題への理解や取り組み方、コミュニケーションの特徴、集中力の持続などが、
ある程度、把握できます。(日常の様子と検査時の様子が同じとは限りません)
こうしたことから、効果的な支援のための参考の一つにできます。
事実上のデメリットは、結果を解釈し、利用する側の問題です。
・ 結果の数字(プロファイル)だけから、背景を考えることなく、
短絡的に、パターン認識のように、支援方法が決められることがあります。うまくいきません。
・ 言語理解の数値が高いので、「コミュニケーションは問題ない」と評価されたり、
「言語を介して指示内容の理解を促すと指示に従いやすくなる」などといった誤った解釈から支援方法が提案されたりします。
・ 特定の認知領域の知的機能を示す指標の間に差があることを発達凸凹と呼び、
発達障害の根拠と説明されることがあります。間違いです。
・ 1年ごとなど、短期間に検査を繰り返し、高く出た結果に基づき、
子どもへの配慮やサポートの水準(=要求水準)を決められることがあります。子どもに過度の負荷がかかることになります。
検査内容を覚えていたり、似たような課題で訓練したりすれば、数値は良くなりますが、実際の能力は反映されていない可能性が高いです。
検査を行う側には、検査を実施できる能力だけでなく、結果を用いて、適切な支援につなげる責任が求められています。このことを、強く認識する必要があります。
学校の先生などは、日常的に、間近で、子どもをみています。
情報量は検査結果とは比べ物になりません。
全般的な学力、読み書きの能力、得意なことと苦手なことなど、把握できるのではないでしょうか。
検査の結果がなくても、子どもの普段の様子に基づいて、適切な支援は行うことは可能ではないでしょうか。
知能検査は、支援のための一つのツールです。結果だけで、子どもの全体像は把握できません。
支援とは、本人の特性や得意・不得意などを考慮した上で、困りごとを減らし、より良く、日々の生活を送れるためのサポートと考えます。
検査の結果(数値)に関わらず、また、周りのひとがどのように思おうとも、
本人が困っていることに対しては、困りごとが減るようにサポートすることが重要なのではないでしょうか。
繰り返しとなりますが、自閉スペクトラム症やADHDが診断できる検査は存在しません。
うちのクリニックでも、知能検査や読み書きスクリーニング検査などを行っています。
ご希望も考慮し、必要があれば検査を行いますが、「とりあえず検査」、「ともかく検査」という対応はしていません。
発熱と咳などの病気に対し、問診と身体診察で診断がつくにも関わらず、とりあえず、血液検査やレントゲンを行うことはありません。
検査は、目的に応じて、必要があるときに行われるものです。
何よりも大切なものは、適切な診断に基づく治療です。
子どもの特性を理解し、困った行動などが起きる背景を分析した上で、具体的な対応方法を一緒に考えて行きましょう。