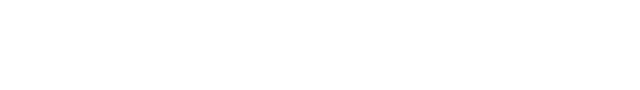受診方法
当院の基本的な考え方など
「診療」(前半) +「お困りの行動などに対する対応のご提案など 」(後半) をセットにして行っております。
同時に、お子さんのできることを増やし、
持って生まれた能力を最大限に発揮し、
お子さんらしく、笑顔で生きられるように
支援することを目的として、診療しております。
お子さんの対応や行動を観察しつつ、
ていねいに診療して説明していきます。
時間の許す限り、ご質問などにもお答えいたします。
診断をお伝えした後、
前を向き、着実に前進していただくために、
こだわり、かんしゃくなど、お困りの行動に対して、
応用行動分析(いわゆる「行動療法」)に基づき、
科学的根拠のある考え方や手法により、
一緒に、具体的な対応や方法を考え、提案いたします。
お子さんやお母さんやお父さんの困りごとが減り、
また、持って生まれた能力を最大限に発揮し、
お子さんらしく、笑顔で生きられるように
支援する出発点として、
診断は必要なものと考えています。
やる気や努力、わがままといった問題ではなく、
持って生まれた脳の機能が多くのひととは異なるため、
苦手なことやできにくいことがあると、
お母さん、お父さんを始め、関わる先生方などに分かってもらいたいため、
診断をお伝えします。
そうした理解がなければ、
やみくもに、がんばらせ、叱咤激励する結果になります。
過大な目標を設定することにもなります。
サポートや配慮にはつながることはありません。
その結果、自己肯定感が低下したり、
いわゆる二次障害を起こしたり、
悔しく残念な結果となることがあります。
診断は、
「発達障害だから仕方がない」といったレッテルを貼るためではありません。
発達障害は薬で治るものではありません。
診断をして、投薬するだけでは問題は解決しません。
注意欠如多動症(ADHD)については薬で症状が改善しますが、
それでも薬物治療で問題が解決する訳ではありません。
「薬がすべて」や「薬ありき」、「薬を出して終わり」とは考えません。
薬については、必要最低限のものだけを処方します。
薬を内服される場合でも、
必ず、効果が出る確率が一番高いと科学的に示されている応用行動分析に基づき、
「具体的な」対応、適切な配慮や支援の方法などを提案いたします。
診断には、大きなショック、不安や心配が伴います。
大きなショック、不安や心配だけを抱えて、ご帰宅して欲しくありません。
慰めや優しい言葉以上に、
前を向くためには、
これまでできなかったことができるようになったり、
かんしゃくやこだわりなどの困りごとが減っていったりする
お子さんの変化が必要と考えています。
そうした前向きの変化こそが希望となります。
そうではなくては、受診していただいた意味はありません。
どうしても診察時間が長くなってしまいます。
みなさん、いろいろと聞きたいことをお持ちです。
「診療」(前半)と「お困りの行動などに対する対応のご提案 」(後半) を合わせ、
初診の診察時間は2時間30分くらいとなります。
5-10分で診察が終了する一般小児科とは全く異なります。
また、当院では、「薬を出して終わり」といった診察、できるだけ多くの患者さんをさばくように診ることはしておりません。
そのため、申し訳ありませんが、予約料をいただいています。
事前に診察の予約もしていただいております。
また、あらかじめ問診票のご記入をお願いしております。
診察を円滑に進め、より良いものにするための重要な資料とさせていただきます。
診察時にはクリニックはいわゆる貸し切り状態としております。
診察終了後の会計時などを除き、
他の患者さまと一緒になることがないようにしております。
お母さん、お父さんとお話している間は、
別室で、受付のものがお子さまと一緒に遊んだりして、お相手させていただきます。
お子さまのことや他のひとの目を気にすることなく、ゆったりと受診していただきます。
初診の流れ
最初、お子さんとお母さん、お父さんで診察室に入っていただきます。
言葉のやり取りが難しい小さなお子さんの場合、診察室のおもちゃで一緒に遊びながら行動観察などを行います。
言葉でのやり取りができるお子さんの場合、お子さんに質問をしながら、回答内容や行動を観察します。
その後、お子さんは診察室から出てもらいます。
別室で、おもちゃで遊んだり、マンガを読んだりして、ゆったりとお待ちいただきます。
受付のものがお相手させていただきます。
小さなお子さんの場合、お母さんやお父さんから離れることを嫌がることが多いため、診察室のおもちゃで遊びながら待ってもらっています。遊びのスペースは十分に確保しております。
お子さんとのやりとりの後、お母さんとお父さんからご心配されていることなどをていねいにお聞きします。
こちらから質問もさせていただきます。
お母さんとお父さんからの聞き取りが終わった後、診断をお伝えします。
診断基準(DSM-5- TR)と照らし合わせながら、診断の根拠についてもご説明します。
診断をお伝えする理由、自閉スペクトラム症や注意欠如多動症(ADHD)に対してどのように考えれば良いのか、基本的な対応方法、今後の不安や心配にどのように向き合うかなどについてもお話しします。
診断に関連するご質問があればお答えいたします。
ここまでが「診療」(前半)です。
概ね1時間から1時間30分です。
この後、応用行動分析(行動療法)に基づく、困った行動への対処方法についての基本的な考え方をご説明いたします。
対応の原理原則となります。対応の基本的な考え方を念頭に置いて、日々、お子さんと接することにより、将来的に大きな違いや差が生じます。
その後、具体的な困った行動、発語なども含め、増やしたい行動などに対し、現状を踏まえ、具体的な対応方法などを一緒に考え、提案させていただきます。
注意欠如多動症(ADHD)や睡眠障害のあるお子さんにつきましては、お薬が有効な場合多いため、お薬に対する考え方、効果と副作用などの説明をさせていただきます。
お子さんのご様子や困りごとの内容から医師としての考えはお伝えいたしますが、内服されるか、されないかのご判断はお母さんとお父さんにお任せしております。
「お困りの行動などに対する対応のご提案など 」(後半)の開始から概ね1時間から1時間30分です。
「診療」(前半)の開始からは概ね2時間30分となります。
予約料について
診療は保険診療となりますが、追加する形で、別途予約料をいただいております。
初診時、概ね2時間から2時間30分を確保し、
診断とその根拠などの説明(「診療」1時間から1時間30分)に加え、
問題行動への対応方法など(1時間から1時間30分)についても、お話しさせていただきます。
再診時、お子さんにお困りごとなどがなく、経過順調で、
主に処方を行うだけの場合(15分診療)には予約料は不要です。
- 初診予約料
平日 22,000円(税込)
土日祝 27,500円 (税込)
※ 当院では「診療」と「お困りの行動などに対する対応のご提案など」はセットとさせていただいております。
一般的な小児科とは診察時間も内容も全く異なるものです。
- 再診予約料
処方がメインの場合(15分診療)には、予約料は不要です。
平日
30分以内 4,400円 (税込)
60分以内 8,800円 (税込)
土日祝
30分以内 5,500円 (税込)
60分以内 11,000円 (税込)
保険診療報酬だけでは十分な時間を確保し、適切な診療をおこなうことができません。
大変恐縮ながら、予約料をお願いしております。
ご理解いただけると幸いです。
なお、予約料については医療費控除、自立支援医療や生活保護医療扶助の対象外となります。
初診の申し込み方法
初診の対象は、予約時点で、小学6年生までで、発達障害もしくは発達障害が疑われ、日常生活で困りごとのあるお子さんです。
再診については中学生も高校生も診ております。生涯を通じて診ていきます。
早期に診断し、できるだけ早く適切に子どもに接していくことが大切と考えています。
初診の対象を小学生以下としている理由は、診察枠には限りがあるため、初診で、中学生や高校生まで診た場合、就学前の子どもや小学生を十分に診ることが難しくなるためです。ご理解いただけると幸いです。
- Step 1 予約フォームの入力
初診予約をご希望される方は下記の予約フォームにご入力ください。
- Step 2 予約日時の調整
1週間以内に、予約の日時調整をメールもしくはお電話でさせていただきます。
予約枠の関係で、受診いただけない場合にもその旨をご連絡させていただきます。
1週間たってもクリニックからメールもしくは電話がない場合、お手数ですが、ご連絡ください。 - Step 3 予約料のお支払い
受診日時が決まれば、予約料の支払いをお願いするメールをお送りさせていただきます。
お支払いはカードでお願いしております。
期日までにお支払いが確認できない場合、申し訳ありませんが、ご予約はお受けできません。 - Step 4 問診票の記入
受診までに、事前の問診票をダウンロードしてご記入ください。
当日、30分ほど前に来て、ご記入いただいても問題ありません。
記載の終了とは関係なく、ご予約の時間に診察を始め、終了させていただきますことをご了承下さい。
できれば診察日前日までに、ご記入が終了した場合、メールまたはFAXでお送りください。・メールの場合、件名に「問診票」と記載し、問診票を添付して送信してください。
・FAXの場合、03-6416-8373まで記載した問診票をお送りください。
診察予約の変更やキャンセルについて
初診予約のキャンセルや変更をご希望される場合には、予約日前日(前日が休診日の場合には2日前)までに、クリニックにメールまたはお電話下さい。
予約の変更は、予約日前日(前日が休診日の場合には2日前)までであれば、1回のみ承ります。
変更については、発熱などの体調不良などやむを得ない場合を除き、ご遠慮ください。
台⾵や自然災害の場合には、診察を行うかについて、ホームページのお知らせをご確認していただくか、当⽇にお電話で問い合わせください。
予約時間の厳守のお願い
診察当日は、予約時間の10分前までにクリニックにいらしてください。
予約時間に遅れた場合でも、当初の予定している終了時間を変更し延長することは致しかねます。
診察の時間が通常よりも短くなります。
また、お子さんご本人がクリニックに来られない場合には診察できません。
ご理解とご了承をお願い申し上げます。
受診される際にお持ちいただくもの
- 保険証、乳幼児・子ども医療証(東京都内にお住みの方)
保険証と医療証のご提示がない場合、自費での診療になります。ご注意ください。
東京都以外から受診される方は、制度上、医療証をご利用できません。
保険証を提示の上、自己負担分をお支払いいただいた後、お住まいの市区役所・町村役場で払戻しの申請を行っていただくこととなります。 - 母子手帳
発達歴を確認させていただくためにお持ちください。 - 先生からのお手紙など
可能であれば、園や学校の様子が分かるものがあれば是非お持ちください。 - 紹介状や発達検査の結果など
療育センター、他の病院やクリニックに受診されている場合にはお持ちください。 - お薬手帳
内服されている場合にはお持ちください。
お会計について
大変申し訳ございませんが、当クリニックはキャッシュレス決済のみです。現金でのお支払いはできません。
VISA、Mastercard、JCBなどのクレジットカード決済でお願いいたします。
再診の申し込み方法
問題となる行動の状況、経過確認の必要性、内服状況などにより、再診までの期間は異なります。
再診も予約制となっております。
診察終了後に次回の予約をお取りいただくか、再診希望のメールをクリニックまでお送りください。
再診に関しても、保険診療となります。
主に処方のみの場合(15分診療)には予約料は不要です。
診察時間が長くなる場合には、再診予約料をいただいております。
診察予約の変更やキャンセルについては、初診時と同じです。
発達/知能検査について
診察時、ご相談の上、実施させていただいております。
2回目以降の予約となります。初診当日に検査はできません。
検査のみ目的で受診されることはお断りしております。
検査を行う心理師は、療育センターなどで長らく勤務されてきた方々のみです。
検査は適切な支援につなげるために行うものです。
検査を行って結果の数値をお知らせするだけでなく、報告書では支援方法などに関してもしっかりと記載します。
検査には、保険診療以外に、下記の検査費用が必要となります。検査予約時にお支払いいただきます。
WISC-Ⅴ:19,800円(報告書付、税込み)
新版K式検査、田中ビネー検査:16,500円(報告書付、税込み)
読み書きスクリーニング検査(STRAW-R):12,100円(報告書付、税込み)
なお、検査費用については医療費控除、自立支援医療や生活保護医療扶助の対象外となります。
発達/知能検査時の流れ
検査当日は、予約時間の10分前までにクリニックにいらしてください。
10分以上遅刻された場合は、検査すべてを実施できない可能性があります。
検査前に、医師による簡単な診察をさせていただいた後(予約料は不要です)、公認心理師による検査を受けていただきます。
検査終了後、結果報告のための診察予約をお取りください。
その際には、大変恐縮ですが、再診予約料が必要となります。
また、検査結果の報告までに2週間程度、お時間をいただきます。
診断書などの文書作成について
文書作成には1週間程度お時間をいただきます。即日発行はできません。
提出期限を確認の上、余裕をもったお申し込みをお願いいたします。
また、文書の種類ごとに、1通につき、下記の作成料をいただいております。
費用
保険は適用されません。自己負担となります。
療育意見書、手帳、特児手当や自立支援医療などの申請書類: 5,500円(税込み)
上記以外(診断書など): 11,000円(税込み)
発達評価書:11,000円(税込み)
ご了承下さいますようお願い申し上げます。
なお、上記の文書作成料については医療費控除、自立支援医療や生活保護医療扶助の対象外となります。
その他のお知らせ
明細書について
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
一般名での処方について
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
医療情報の活用について
当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療をおこなっています。