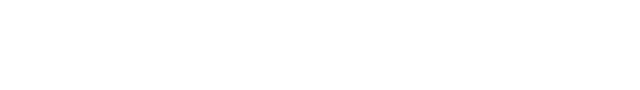注意欠如多動症(ADHD)
注意欠如多動症はADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)と言われます。
アメリカでは、子どもの5-6%程度が該当するとされており、日本でも同様と考えられます。
診断基準を簡単に示すと次の通りです。
- おうちや学校などの複数の場所において、
- 年齢や発達の程度に見合わない程度に、①不注意や②多動性および衝動性が見られ、
- おうち、園や学校での生活において困難(不適応)が生じている状態
① 不注意とは
- 見逃しや見過ごしなどうっかりミスが多い すぐに気が散り、集中できない
- 話しかけられたときに、聞いていないように見えることが多い
- 順序立てて課題や活動を行ったり、時間の管理ができなかったりする。
- 忘れ物や物をなくすことが多い
- 指示したうちのいくつかが抜けていたり、約束したことを忘れたりすることが多い
などです。
② 多動性および衝動性とは
- 手足をそわそわ動かしたりして落ち着きがない
- 席に座っていられない
- 不適切な場面で走り回ったり、高いところへ登ったりする
- じっとしていられない
- しゃべりすぎる
- 質問が終わる前に出し抜いて答え始めてしまう
- 順番を待てない
- 他人のしていることをさえぎったり、じゃまをしたりする
などです。
ADHDもスペクトラム症と考えられます。
程度や頻度が著しい場合に、「特性が強い」という判断になります。
就学前の子どもに対する診断は慎重に行います。
ADHDも持って生まれた脳のはたらき方によるもので、育て方の問題ではありません。
「なぜできない」、「何回同じことを言わせるの」など、叱られたり、注意されたりすることが多くなります。
ADHDに対しては症状を緩和する薬があります。
しかし、内服により問題がすべて解決する訳ではありません。
薬は、風邪などの発熱時に内服する解熱薬と同じような役割です。
解熱薬にはウイルスや細菌をやっつける効果はありません。
熱の上がる体の仕組みをブロックし、数時間、体温が上がらないようにして、発熱による不快感を緩和するためのものです。
ADHDのお薬も、症状が緩和されることにより、子どもが日々の生活を過ごしやすくするためのものです。
困りごとの原因となっている特性をなくす効果は全くありません。
したがって、内服する場合でも、関わる大人が本人の特性を理解した上で、まずは、気が散りにくい環境を整えたり、一緒に忘れ物を減らす工夫をしたりするなど、不注意や多動・衝動性に対して、困りごとを少なくする工夫を続けることが不可欠です。
繰り返しになりますが、薬だけで解決することはありません。
また、ADHDの子どもは、自閉スペクトラム症の特性を持っていることが多いです。
ADHDと自閉スペクトラム症の特性の比率は子どもによって異なります。
一般的に、多動・衝動性については、10歳くらいになると自然と落ち着いてくることが多いです。
そうなると、自閉スペクトラム症の特性である対人関係の困難さなどがより目立つこともあります。